
第37回 雷のヘソ
民俗学者・酒井卯作
(題字・イラストも)
古い方なら記憶にあるかと思います。雷の鳴る日、こんな歌が流行していました。
嬶(かかあ)よ蚊帳(かや–)吊れ 雷様だ
線香立ててヘソかくせ
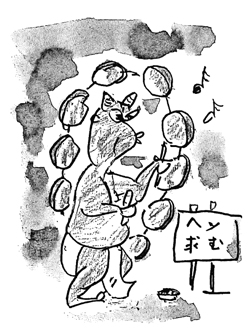 |
雷がゴロゴロとなるうちはまだ安心ですが、バリバリという烈しい音に変わると、地球が二つに割れそうで、そりゃ恐ろしいものでございます。
恐ろしいのは音だけではありません。その雷が人間のヘソをとるというのです。雷はなぜ人間のヘソを欲しがるのか。
通説によれば、ヘソは人間の体の中心部にあって、母親からもらった大切なもの。これがなければまともに生きていけない代物(しろもの)だといいます。つまり人間の象徴としてあるのがヘソだということです。
雷はその反対に、ヘソはありません。だから下界の人間のもつヘソが珍らしいのでしょう。ではなぜに雷にヘソがないと考えたのか、その根拠を申し上げます。
雷は神様の末えいです。私たちはカミナリと呼びますが、以前はナルガミといって、神の名が主語になりました。清少納言の「枕草子」などにも「せめておそろしきもの、夜鳴る神」(二六四)とあるし、奄美諸島では今も「なるかんがなし」といって恐れています。つまり、落ちぶれた神様なのです。
ちなみに日本の古典「竹取物語」の主人公かぐや姫は、竹の中から生まれたのですから、当然おヘソはありません。
成り足らざるものを補充したいのが人間も神様も同じこと。神様がヘソを狙うのだったら、人間は何とかして大事なヘソを守ろうとします。その方法はあるのかといえば、あるのです。
さきに紹介した歌は続きがあります。下村作二郎氏はこう述べています。歌い終ると蚊帳の中で腹ばいになって、つまりヘソを畳の方にしてクワバラ・クワバラと唱えるといいます(旅と伝説6・10)。こうすれば雷にはヘソは見えませんから、まず大丈夫です。
クワバラというのは、たぶん桑原のことです。桑の木は悪霊から身を守る力があると信じられていたようで、私はそこで雷について古い話を思い出します。私の生家、長崎県西海町、今も昔も農村です。まだオフクロが生きていた頃、祖母は畑仕事中に雷が鳴り出すと、急いで家に戻って、座敷の真中でチョコンと坐っていたそうです。
どうして、とオフクロが聞くと、「床の間に桑の木の建材で造ったところがあるけん、ここなら雷は落ちんと」といっていたとオフクロは笑っていました。問題は桑の木です。
ちなみに辞書で扶桑という字をひくと「昔、中国で、東海の日の出る所にあると伝えられる神木」とあります。
さらにくわしくは、南方熊楠翁が調べた記録があります。これによれば、中国の「拾遺記」という本に、西海の浜に桑の木があって「直上千尋、葉紅、ク棋紫ニ、萬歳一実、之ヲ食ハバ天ニオクレテ老ユ」(南方熊楠全集2-54頁)とあります。
つまり富士山よりも高い桑の木があって、この実は一万年に一度実がなり、それを食べたら老いることはない不思議な神木なのです。おそらく強情な雷といえども、この巨大な神木の名を聞けば沈黙せざるをえないのでしょう。桑原の呪言は効果がありました。
それだけではありません。沖縄地方では雷が鳴るとさらに「桑の木の股」と唱えます。木の枝の分れた部分は、なぜか妖怪は恐れをなす部分なのです。奄美地方では昔から木の股を嫌がってそこに釘を打ちつけたという話があります。
話をここまでもってくると、私は思いだす文献があります。それは九世紀頃に完成したという「日本霊異記」という本です。これは当時の景戒という僧侶の手になった仏教の説話集で、岩波書店の「日本古典文学大系」の中に収録されています。その本の巻頭に「雷を捉ふる縁」という一節があります。
およそ仏教説話とも考えられない愉快な物語なので、要約して紹介してみます。ご存知の方もどうぞ思い出してください。
雄略天皇の時代、これは記紀の時代、五世紀頃の第二十一代の天皇と伝えられています。その天皇に仕えた栖軽(すがる)という侍者がいました。
ある夜、雷がえらく鳴るので、栖軽は天皇を案じて部屋に入ると、天皇はたまたま皇后とマグワイの最中だった。栖軽はおそらく部屋に入るについては声をかけたのだと思いますが、天皇はマグワイに夢中だったのか、雷の音がはげしかったのか、栖軽の入室の合図には気がつかなかったのでしょう。
天皇は少し恥ずかしかったので、栖軽に「あの雷を捉えて来い」と命じます。
栖軽はあちらこちらと雷の音をたよりに探し出し、やっと捉えて雷を籠に入れて天皇の許に帰えります。天皇はその雷を見ると、形相は鬼のようにけわしく、光輝いているので天皇は恐ろしくなり、雷に供物をして天に戻しました。その後、栖軽も死亡したので、天皇は栖軽のために墓を作り、木の柱の標識を立て、そこに「雷を取りし栖軽の墓」と書きました。
ところが、雷はその碑文を読んで猛然として怒った。自尊心を傷つけられたのです。こんどは前にも増して雷鳴をとどろかせ、大暴れ、暴れているうちに、不覚にもその木の柱が二つに割れて、雷はその割れ目にはさまれて動けなくなってしまいます。暴れるのも度がすぎたのです。
天皇はまたその雷に供物をして天に帰し、栖軽の墓に「生きても死んでも雷を捉えし栖軽の墓」というように書き替えて標を立て直したといいます。
日本人が描く物語は、いつの時代でも無邪気です。人間と神は今よりももっと親しかったと思います。そして私が注目したいのは、当時の墓標というのは、貴族の墓といえども、一本の柱のような質素なもので、雷が落ちたら割れてしまうような、かんたんなものだったということです。石塔以前の古い墓標をこの物語の中に垣間みられます。
--------------------------------------------------------------------
酒井 卯作(さかい・うさく)1925年、長崎県西彼杵郡西海町生まれ。
本会理事。民俗学者。
著書
南島旅行見聞記 柳田 国男【著】 酒井 卯作【編】 森話社 2009年11月
琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井 卯作 第一書房 1987年10月
稲の祭と田の神さま 酒井卯作 戎光祥出版 2004年2月
など多数。

