
第35回 仏檀と位牌(その二)
民俗学者・酒井卯作
(題字・イラストも)
日本の多くの家庭では位牌を作って拝んでいます。その位牌は仏檀に阿弥陀仏と一緒に供えて拝むのですが、問題なのは、仏教の象徴としての阿弥陀様と、穢れの強い死者の位牌を一緒に祀ることの不自然さです。今回はその位牌について考えてみます。
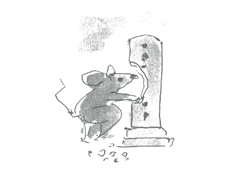 |
民俗学界では、古くから一本花に注目していました。なぜか。それは新潟県佐渡などの各地ではこれを「位牌花」と呼んでいるからです。つまり位牌以前には、この一本花が位牌の役割を果たしていたらしいという想像に由来します。例えば死者の寝ている布団などの上に、今は刃物などおいて魔除けとしていますが、往々にして一本花を代りにおくところもあります。一本花、一膳飯、など、不吉な意味を伴うということはすでに書きました。
もしそうだとすれば、一本花は日本製の位牌ということでしょう。日本製といえば首をかしげる人も多いと思いますが、現在用いられている日本の位牌は、中国大陸の儒教の影響によるもので、仏教とは少々性質が違うと考えられます。沖縄を含めて、位牌のことを、神位・神牌・霊位など、その名称からでも、儒教の臭いを感じさせられます。
では、その位牌の歴史はどうだったのか、江戸時代の国語辞典ともういうべき「倭訓栞」(わくんのしおり)をみると、位牌について次のように書いてあります。
「位牌の字、朱子語類(しゅしごるい)に見えたり。天竺の制法にもなく、神主の古式にもあらず、今いふところの位牌の形は宮殿又はほこらの体を模せし物にて、神道の霊位と号する物なり」
とあり、さらに、この制度は中世以来、公家などの上流社会では祀られたけれども、庶民社会では各家に位牌を祀ることはなかったといい、最後に「仏家に此名を借りて亡者の神主に名ずくる也ともいへり」と結んでいます。
要約すれば、中世以前の支配者の家は別として、民間では位牌はなかった。それを仏教が借用して死者のための供養といって転用したということになります。これを裏書するように、江戸時代の旅行家、菅江真澄(すがえますみ)の「遊覧記」(五)には、秋田県男鹿半島の先端にある漁村の風習があります。それには
「門の柱や板戸に掲げた札が、逆さになったり裏返しになったりしている中に、亡き霊の名を書いた紙札もあるのは、ここのならわしかと聞くと、そうとは知らずにはったといって、法名を破りとった」
とあります。位牌の普及する以前の形は、およそこんなもので、今のように丁重な扱いをうける位牌とは大きな差があります。男鹿地方で、人の悪口をいうとき向う面(つら)・肛門(けつ)・位牌・病(やま)いなどという言葉があり、位牌もその中に入っているのは、位牌がいかに低く見られていたかということを教えてくれます。日本各地にある位牌山は、頂きが尖った山をいいますが、この山を持つことを嫌がったことと考え合わせると位牌に抱く感情がどんなものだったかがよくわかります。
日本も南に下るともっとはっきりします。例えば鹿児島県奄美大島を見ましょう。この島の南にある久根津の久家実知(ひさいえさねとも)さんから、生前に聞いた話ですが、この土地で仏檀を作ったのは昭和2年頃だといいます。
じつはその頃、古仁屋の町にお寺ができたためです。それまでは位牌の必要な人は、古仁屋の町の雑貨店で買い求めました。当時は位牌といわずにフダ(札)と呼んだものです。その札は盆がすむと、天井裏などに挿しこんで保存した。これが位牌の実状でした。
さらに南に下って沖縄でもほとんど変わりません。
沖縄では位牌はトゥトゥメと呼ぶ例が多いのですが、亡くなった人の名前と死亡年を札に書いて、それを縦に並べるか横に並べるかして祭檀に祀ります。今ではこのトゥトゥメは、沖縄の人たちにとっては、命にも代え難い大切なものになっています。
そこで照屋寛範(てるやかんぱん)氏の「沖縄の宗教・土俗」(昭和32年刊)を参考にしてみると、位牌の成り立ちが少しわかります。例えば幕末の頃の位牌が、多くの人たちに「位牌ワンダイン」と呼ばれるくらい、煩わしい存在だったということです。ワンダインは荷物や年寄りなどをもて余すことで、位牌もその一つだったのです。その煩わしい一例をあげてみます。
幕末の頃、奉行所から「位牌改め」がありました。お役人が農家を廻って位牌の有無を調べるのです。農家ではほとんど位牌など祀らなかったので、まず位牌を祀っている家の裏口から手渡しして位牌を借りて検査をすませたといいます。位牌に何と書いてあろうがおかまいなし。ただその札さえあれば良かったのです。第一、農民は字が読めなかったのですから。
その位牌改めがだんだん厳しくなると農家も困ります。当時の童歌(わらべうた)に「1貫目のお金で買ってきたトゥトゥメ(位牌)を泥棒にとられてしまった。どうしよう」という意味の歌が流行したのもその頃です。
位牌はこうして、しだいに固定して家に祀るように変化してきます。政治の力で死者の祭りが強制されていくのです。
日本の多くの人たちが、大切にして拝み続ける位牌の歴史には、複雑な内容があります。最初は中国の儒教によって、7・8世紀頃上層階級に支持され、そして仏教はそれを横取りをして位牌の祭りを仏教化してしまった、というような流れが見えます。「続日本紀(しょくにほんぎ)」によれば、天平勝宝八年(749)に孝謙(こうけん)天皇が亡くなったとき、仏教に帰依していたために、これまで死後に送られた諡(いみな)は奉らず、法名を法基として奉ったという記録からも、儒教から仏教への移行する様子が垣間みられます。
しかしこうした流れは庶民の信仰とは直接関わらなかったようです。そこで初めに述べた位牌花の話に戻りましょう。
かつて死者に供えられた位牌花と呼ぶ一本花は、たぶん今の位牌の原形だったかもしれないということです。花は香りを残して、やがて土に帰っていきます。人もまた浮世の風に流されて土に帰っていきます。花も人間も同じ運命をたどる生きものです。私たちの先祖は、その美しい花になぞらえて、自分たちの死を優雅なものにしようと考えたのでしょう。そこに日本人の心の美しさが見えます。
(「仏檀と位牌」おわり)
--------------------------------------------------------------------
酒井 卯作(さかい・うさく)1925年、長崎県西彼杵郡西海町生まれ。
本会理事。民俗学者。
著書
南島旅行見聞記 柳田 国男【著】 酒井 卯作【編】 森話社 2009年11月
琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井 卯作 第一書房 1987年10月
稲の祭と田の神さま 酒井卯作 戎光祥出版 2004年2月
など多数。

