
第31回 花咲爺と散骨
民俗学者・酒井卯作
(題字・イラストも)
「昔、のぅのぅ」
「あいあい」
昭和の初め頃、私が生まれた長崎県の西海町の田舎では、まだ家には電気がありませんでした。それで、石油ランプを消して暗くなった夜の寝床で、一緒に寝ている私に語って聞かせる父親の昔ばなしの語り初めは、いつもこの「昔、のぅのぅ」から始まります。「あいあい」の返事がなければ、話はそれっきりで終りです。
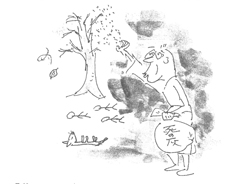 |
父親が知っているのは「猿蟹合戦」と「花咲爺」の二つだけで、いつもこの二つのうちの一つを語ってくれました。ノミに噛みつかれながら過ごす冬の夜長は、この昔ばなしの故に慰められた覚えがあります。
春が待たれるこの頃です。その季節に合わせて、この「花咲爺」の話をしてみます。皆さんもすでにご承知だと思われるこの話には、いろいろ難しい意味がありそうです。日本各地に似た話がありますが、ここでは青森県五戸地方の話をとりあげて考えてみます。
昔、むかし。お婆さんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃が流れてきました。お婆さんはそれを拾って帰ると、間もなくその桃から犬が一匹生れました。子供のいないお爺さんとお婆さんはその犬を大事に育てていると、やがて大きな犬に成長しました。
あるとき、その犬はお爺さんを畑に案内して、ここを掘れという格好をする。いわれたとおりに掘ってみたら、大判小判の宝物が出てきました。
お隣りの欲張り爺さんはそれを聞いて、その犬を借りて自分の畑を掘ったら、蛇やムカデが出てきました。欲張り爺さんは怒って、その犬を殺してしまいます。
親切な方の爺さんはそれを聞いて悲しくなり、その犬のために塚を築いて、そこに一本の松を植えました。ところがその松は一晩のうちに大きな大木になったので、お爺さんはその松の木で臼を造り、それで餅をついたら、その餅が大判小判になりました。
隣りの欲深爺さんはこの臼を借りて餅をついてみたら、餅は牛や馬の糞になってしまいます。怒った欲張り爺さんはその臼を焼いてしまう。
親切な方の爺さんは、焼かれた臼の灰をもらいうけて枯木に撒いたら、花がいっぱい咲きました。通りがかった殿様がそれを見て、たくさんの褒美をくれました。欲深の爺さんもそれを真似て枯木に灰を撒いたら、灰が殿様の目に入って怒られ、とうとう牢屋に入れられてしまいました。
これで話はおしまいです。昔ばなしは夢が浮き沈みする豊かな海のようなもの。子供たちはその中から、人生の生き方や歴史を学びとるのです。花咲爺の昔ばなしも同じだと私は思います。その理由を次にあげてみます。
この昔ばなしの主役は犬です。なぜ猫ではなくて犬なのか。それは東アジアでは犬に対する信仰があったからだと思います。犬は財宝を発見します。また犬と結ばれる女性の話はいくつもあります。曲亭馬琴の「南総里見八犬伝」などは、私は少年の頃、熱中して読んだ本の一つです。
犬と結ばれる話は沖縄の離島にも分布していて、犬はさらに水に不便だった島で、泉を発見する動物でもありました。犬は宗教的な意味をもつ理由の一つに、日本では人が死んで三十三年忌の弔い上げに、犬塔婆といって、先端が二つに分かれた木を墓地に立てます。
なぜ塔婆に犬の名をつけるのかは、死者の魂が犬によって天国に導かれることを意味するのだと私は考えています。それは朝鮮半島の高句麗古墳の壁画に犬が描かれているのでもそれがわかります。
花咲爺の昔ばなしの中でさらに注目されるのは、犬を埋葬した塚の上に木を植えたということです。日本では庶民が墓所に石塔を建てたのは江戸時代。それ以前は埋葬地には自然石、もしくは木を植えて目印としました。
例えば、江戸時代の1780年に刊行された山岡浚明(しゅんめい)の「類聚名物考(るいじゅうめいぶつこう)」(凶事四)という本には「亡人のなき跡のしるしに、塚墓に木を植る事、その来るや久し」とあります。つまり久しい昔から、埋葬地には石塔ではなく、木を植えていたのです。
では、「久しい昔」とはいつ頃か。歴史にみられるのは721年に崩御した元明天皇の遺命に、山陵には「皆常葉の樹を植えよ」(続日本紀(しょくにほんぎ)・巻八)とありますから、常緑樹、つまり松を植えたことが想像されます。
この昔ばなしの中の爺さまが、死んだ犬の塚の上に松を植えたというのは、当然人間の伝えてきた風習を反映してのことで、日本の古墳の上には、ほとんど松が生えていることで合点していただけると思います。
だからこんな怖い話も生れます。宮城県の伝説を集めた「郷土の伝承」(一)によれば、村の老人の話として、夜になると野の古松の木の上から「おぼさってぇ、おぼさってぇ」という声が聞こえるときがあるそうです。この古松の木の根元にはきっと死骸があるにちがいありません。
さて、この花咲爺の昔ばなしの本命は、なんといっても動物の埋葬地に植えた木の灰を撒いて、宝物を得たという筋書です。別名「灰撒き爺さん」とも呼びますが、私どもはこの話の底には散骨という行事を連想させられます。もともと死者の遺骨を空中に散らす自然葬のような弔い方があって、そこから生れたのが、この花咲爺の昔ばなしだろうということです。
花咲爺の昔ばなしは隣りの中国にもあります。「枯樹開花」と呼んで、犬は桃からではなく竹から生れたという筋書で、人物も善良な兄と悪い弟の話になっていると高橋盛孝氏はいいます(昔話研究一)。
そうだとすれば、花咲爺の話は中国に発したとも考えられますが、しかし一つの話が伝播していくためには、それを受け入れる素地が必要です。やはり日本でも似た話があったのでしょう。散骨ということを知らなければ花咲爺の昔ばなしは生れなかったと思います。
時代は変わります。この情緒のある昔ばなしの時代を捨てて、今、原子力発電所の死の灰と直面しています。花の咲く灰と、死を呼ぶ灰のいずれを選ぶか。いままさに春爛漫(らんまん)の季節を迎えようとしています。良い年になりますように。
--------------------------------------------------------------------
酒井 卯作(さかい・うさく)1925年、長崎県西彼杵郡西海町生まれ。
本会理事。民俗学者。
著書
南島旅行見聞記 柳田 国男【著】 酒井 卯作【編】 森話社 2009年11月
琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井 卯作 第一書房 1987年10月
稲の祭と田の神さま 酒井卯作 戎光祥出版 2004年2月
など多数。

