
第14回 情死の美学
民俗学者・酒井卯作
(題字・イラストも)
死ぬほど好き。政治生命をかけて。これがいちばんアテにならない言葉。私たちは「死ぬくらいに」という言葉を安易に使いすぎます。そんな簡単に人は死ねるわけはないのです
ちなみにドイツの作家、ダンツィオが書いた「死の勝利」という和訳の小説があります。死ぬほど愛しあった二人が、いよいよ断崖から身を投げようとしたとき、女は突然死ぬのを嫌がって抵抗します。人殺し、などと叫んで暴れる女を抱き抱えて、もつれあいながら断崖から二人とも落ちていくところで話は終ります。
死に直面したとき、初めて死の恐怖を知るということでしょうか。同時にそれは生きるということへの執着を実感することでもあります。
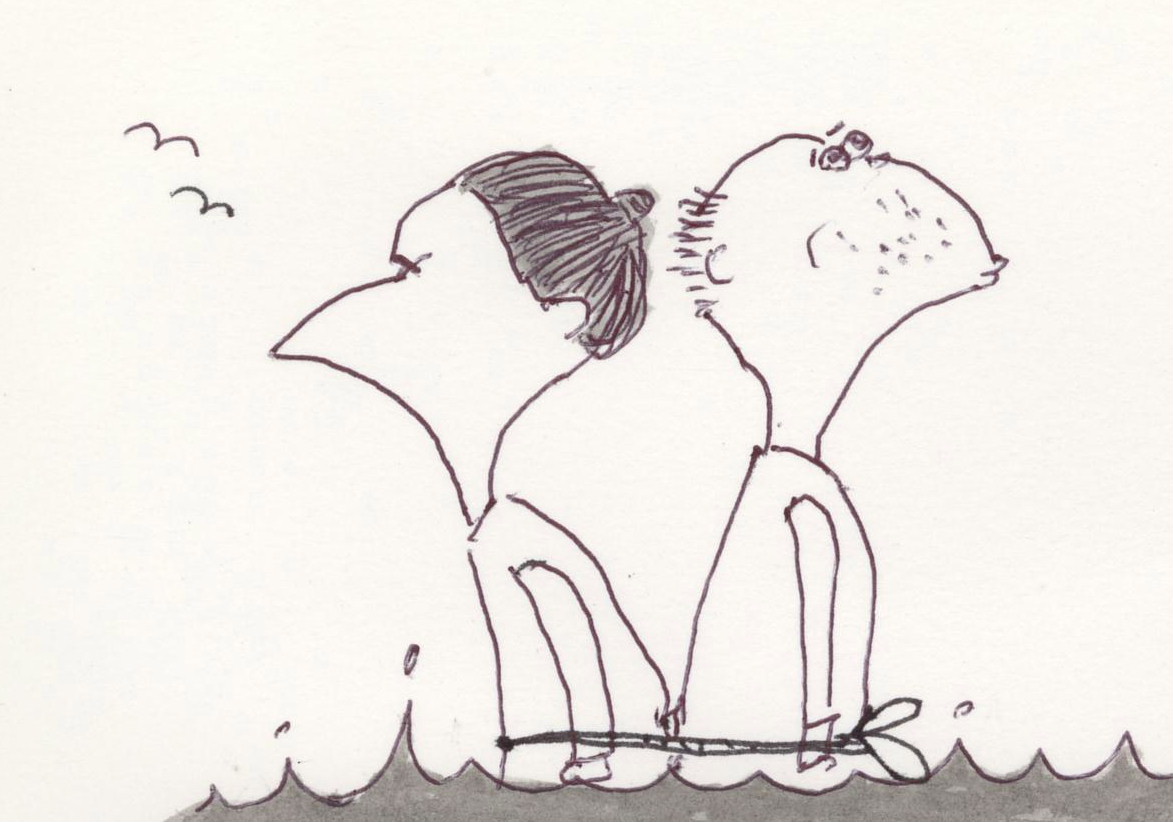 |
似た話が沖縄県の名護市にもありました。許婚のある小学校の教師が、酒場の女と深い仲になってしまった。どうにもならないというので、酒場の女と心中しようということになった。遺書を書いて、二人で一緒に海に入っていきます。
ご存知のように、沖縄の海は珊瑚礁の遠浅です。二人で抱き合って腰の高さぐらいの深さまで入ったとき、男はフト考えた。ここで死んだら楽しいことはなくなる。すべてがおしまいだ。そう考えて、女に心中を止めようというと、女は「有難うございます」と答え、そこで二人は心中するのを止めたといいます。
ありふれた心中未遂の話ですが、わからないのは、あのとき「有難うございます」と答えた女の気持ちです。死を覚悟して海に入ったはずなのに、取り止めとなって、なぜお礼をいったのだろうか、ということです。きっと、人間は生きるという本能があって、それが突然甦ってきたということではないでしょうか。
男はその後発奮して、沖縄の県会議員として活躍した仲田徳三氏。女の消息はわかりません。
心中とは上方の言葉。関東ではあいたいし相対死といいます。雑誌では情死ともいいました。好き人同士で死ぬということは悲しくもあり、美しくもあります。私もそうしたいです。日本では心中にせよ自殺にせよ、自ら命を断つということは罪でした。だから佐渡のように墓をたてることは禁止されていました。つまり自然死だけがほんとうの死だったのです。
これは沖縄でも同じことで、日清戦争のときの戦死者も、事故死と同じように扱われたことがありました。事故死は素直に島内には入れず、一晩は浜に置いてから葬ったものです。
かつて義弟が癌で死ぬ直前、絞るような声で「一ヶ月でも一日でもいいから、生きたい」といって果てました。急がなくてもその日は必ず来ます。生きてさえいたら、そのうち連れ添うた者も死ぬでしょうし、そしたら再婚もできるといもの。諦めたらおしまいです。
再生 第78号(2010.09)
--------------------------------------------------------------------
酒井 卯作(さかい・うさく)1925年、長崎県西彼杵郡西海町生まれ。
本会理事。民俗学者。
著書
南島旅行見聞記 柳田 国男【著】 酒井 卯作【編】 森話社 2009年11月
琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井 卯作 第一書房 1987年10月
稲の祭と田の神さま 酒井卯作 戎光祥出版 2004年2月
など多数。

