
第33回 冥土の入口で
民俗学者・酒井卯作
(題字・イラストも)
人は別れるときに、黙って別れることはしません。何らかの挨拶が必要なのです。それに、場所に応じて別れの言葉も違います。
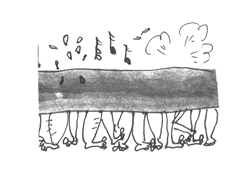 |
例えば病院で診察が終わったとき、医者は患者に「ハイ、お大事に」。この言葉が慣例のようです。飛行機に乗って目的地に着いて降りるとき、客室乗務員さんは出口に立って、かならずこういいます。「またの出会いをお待ちいたしております」。そういって、ニコッと笑います。これを聞くと、また乗ってみたい、そんな気持になるものです。
それでは警察に捕まって釈放されるときはどうか。警官はけっして「またの出会いを──」なんていいません。別離の言葉は、その状況で区別されます。もし病院で医者が患者に「ではさようなら」なんていったら、その患者はその言葉に落胆して、病院には行かないでお寺に行くでしょう。
問題は人が死ぬときです。今は人が亡くなると、坊さまが来てお経を唱えてくれます。このお経が死者との最後の別れです。福井県の若狭大島では、病人が息を引きとっても、坊さまが来て枕経を読む前はまだ病人で、枕経が終わると仏になったといって、枕を西方に直したといいます(日本民俗学2-2)。
これで人間は完全に死亡したことになります。しかし別の見方もあります。明治13年の「三重県習俗慣行調」によれば、「屍棺ヲ墓所ニ送ルマテハ病者トナシ。墓所ヨリ歸宅シテ初メテ死者トスル」とありますから、坊さまのお経とは関係なく、死が完了することがわかります。
葬式仏教が日本人の死を支配する以前に、私たちの死の世界はもっと情緒がありました。生きている人と、亡くなる人の間には、他人を入れないで、身内だけでの別れがあったのです。その中でいちばん有名なのは「声かけ」です。
危篤状態になって、もうこれが最後というとき、その病人の名前を呼ぶのは今でもあります。別名「魂呼ばい」ともいいますが、屋根に登って危篤の病人を呼ぶのです。この風習は北は青森県から沖縄県まで、全国的に広く分布しています。私がじっさいに行なった人の話は、鹿児島県の沖永良部島の国頭の郵便局長さんでした。一度だけその経験があったそうですが、海での遭難事故で亡くなった人がいたので、屋根に登って海の方に向って大声で名を呼んだ。そしたら、何となく魂が戻ってきたような感じがしたと語ってくれました。
屋根に登って危篤の病人の名を呼ぶのは、かなり効きめがあったのかもしれないというのは、和歌山県東牟婁郡請川村(ひがしむろぐんうけがわむら)(現 田辺市本宮町(たなべしほんぐうちょう))の例があります。
この村で70歳ばかりの弥七郎という男が急病で死にそうになったので、例のややこしい声かけの行事をした。そして魂を呼び戻したのです。ところが命はとりとめたものの、元気になった病人の記憶も話も以前とまったく違います。
そこで縁者が集まっていろいろ話合っていると、わかった。ちょうどその頃、この村の山奥で働いていた同じ名前の弥七郎という男が亡くなって、まだ魂が消えてなかったとみえて、その人の魂が間違って別の弥七郎さんに入れ替ったということです。神様もそそっかしいと思います。生き返った本当の弥七郎さんは、それから10年ぐらいは生きていたそうです。(民間伝承12-8)。
この世に残る人が、去って帰らぬ人にかける最後の言葉。沖縄でも「声をかける」とか「魂をあびる」などといいます。
八重山地方の川平では死がさし迫ってくると、2人の婦人の1人が、1合ほどの米を臼で、わざと大きく杵の音をたててつきます。その音を聞いて、危篤の人はあの世に旅立って行くといいます。他の1人は屋根の桁(けた)に両手をかけて3度、危篤の人の名前を呼びます。それで反応がなければ、死です。
そこでこんなことを沖縄ではいいます。人の名を3度呼ぶときは死人を呼ぶとき。夜1声だけで自分の名を呼ばれたら幽霊の声。同じ名前を呼ぶのにいろんな作法があるのです。
死ということには、人間と霊魂との間に行われる一種のドラマがみられます。その中で坊さまの読経では癒(いや)されない、もっと素晴らしい別離の仕方はいくつもあります。岡山県加賀郡の農村では、以前は妻が先に死ぬと、出棺のとき、夫は「もう暇をやるぜや」と声をかけるし、夫が先に死んだとき妻は「もう暇をもらうぜや」と最後の言葉を述べるそうです。
夫婦の死に別れの辛さ、しかしけじめをつけなければならない悲しい決断。生身が引き裂かれる思いを抱いている人は今も多いと思います。生き残る人はともかく、死出の旅路に出る人は、どんな思いを抱いて行くのか。これを山形県の酒田市の沖にある飛島にあの世の入口を見ましょう。
飛島は晴れた日には、西の海に幽かに見えるそうです。昔から「羽後の飛島酒田の向い、向い同志で海路は十里、羽がなければ飛んでは行けぬ」の歌が、飛島の不便な遠い島だということを物語っています。
その島の西端にサイノカワラと名づけられた葬地があり、墓場となっています。その墓地に通じる勝浦というところの道端に、元村長もしたことのある斉藤という人の家があった。深夜、ふと耳を澄ますと、何かブツブツと小言をいって通って行く人がいる。翌日になると心当りのあるその人がかならず死んでいくといいます。あるときは泣きながら通って行く女がいたり、ときには鼻歌を歌いながら行く人もいたそうです。
生きているとき、その生きざまを引きずってあの世に行く人たちの魂が、このような声を残すのでしょう。
さて、皆さんが亡くなったとき、ブツブツ小言をいいながら行くか。鼻歌を歌いながら行くか。それとも……。
もう秋の夜長が始まります。
塚もうごけ わが泣く声は秋の風 芭蕉
--------------------------------------------------------------------
酒井 卯作(さかい・うさく)1925年、長崎県西彼杵郡西海町生まれ。
本会理事。民俗学者。
著書
南島旅行見聞記 柳田 国男【著】 酒井 卯作【編】 森話社 2009年11月
琉球列島における死霊祭祀の構造 酒井 卯作 第一書房 1987年10月
稲の祭と田の神さま 酒井卯作 戎光祥出版 2004年2月
など多数。

